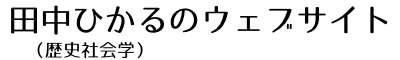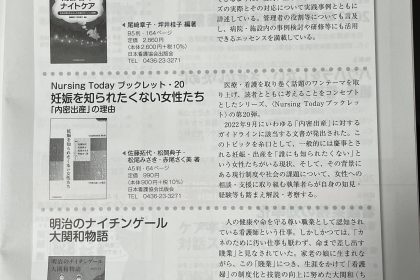NHKスペシャル『出生前診断 そのとき夫婦は』
妊娠中の東尾理子が、胎児のダウン症の可能性を公表。その後、血液検査だけで染色体異常の確率が99%の精度でわかる検査が日本でも導入されるというニュースが流れ、新聞や雑誌で「出生前診断」が話題になっている。
新聞の投稿欄は、たびたび、“出生前診断でダウン症とわかったときは、ショックを受けたけれど、生まれてきたわが子は、家族に幸せを運んできてくれました”といった意見を掲載している。
9月16日放送のNHKスペシャル『出生前診断 そのとき夫婦は』。
これも新聞の投稿と同じ方向性なのだろうな、と思いつつ観た。
方向性は同じだったが、説得力が違った。
番組は、大阪にある「出生前診断とその後のサポート」を専門とするクリニック(分娩も治療も行わない)を中心に構成。
私は、出生前診断が即、中絶につながるとは考えていないが、出生前診断、とくに最新式は高額なので、「それ(だけ)をビジネスにするのか」と、少し引いた。
このクリニックを訪れる患者のうち、1割が胎児に異常があると診断され、うち8割が中絶するという。
番組の後半、一組の若い夫婦が登場。
妻は、二分脊椎症を患っていて、装具をつけないと歩けない。
病気のせいで、子どもは持てないものと諦めていたが、妊娠し、とても喜んでいた。
妻に、前出のクリニックでの出生前診断を勧めたのは、母親だった。
病気の娘に、病気の子どもを育てることは、難しいと考えたからだ。
検査の結果、胎児も二分脊椎症だということがわかった。
妻は、本当は産みたいのだが、「(夫の両親に)孫だけでも健康な子を見せてあげたかったので、本当に申し訳ない。私の親にも、娘だけでなく孫も病気なんて、みんなに申し訳ない」と、周りを慮る。
夫も、本当は産んでほしいのだが、そう伝えてしまうと、妻の意志を尊重できないと考え、口にできない。
診断の3日後、夫婦と、夫の両親、妻の母親の5人でクリニックを訪れ、医師を交えて5時間に及ぶ話し合いがもたれた。
最初に口を開いたのは、夫の父親。「われわれも年をとっていく。この先、お手伝いできるかどうか」。
夫の母親も、「楽しくしていればいいこともあるし、希望をつなぐってそういうことだと思うし。生まれたら、一生やもんな」と暗に(露骨に?)中絶を促す。
妻の母親は、「この子に子どもができるのをほんまに楽しみにしてきた」と涙ながらに口にするが、「産みなさい」とは言えない。
黙っている若夫婦に、医師が「夫婦でお互いに気を遣って声に出さへんかったら、あかんと思う。ちゃんと話してみ」と言い、夫婦を残して、親たちは退室。
ここで初めて、夫が妻に「産んでほしい」と本心を明かす。
医師の計らいで、まず妻の母親だけが部屋に戻り、妻は母親に「どっちの結論出してもいい?」と尋ね、母は、「かまへんで。お母ちゃんはいいよ」。
若夫婦と、妻の母親の気持ちは出産へと傾いた。
時間をかけて、当人はもちろん、家族の心も整理し、最良の道を探る。結論を急がない。
きちんと「その後のサポート」にも力を注いでいるこのクリニックの女性医師に、気概を感じ、当初の「誤解」を反省。
結局その日、夫婦と親たちは結論を出すことができず、翌日、中絶の可能性も考えて予約を入れていた、別の産科へ行った(ここから先は、一家の回想による)。
そこで中絶の措置についての説明を受けている途中、妻が倒れてしまう。
その「健気さ」「いじらしさ」がたまらなくなった夫の母親が発した「産むか」のひと言に、妻が「ありがとう」と答え、結論が出た。
数ヵ月後、無事、女児が誕生。
出生前診断直後の波乱が嘘のように、家族みんなが笑顔だった。
クリニックの果たした役割は大きい。
おそらく、出生前診断を受けないまま出産していたとしても、この家族は、遅かれ早かれ笑顔になれただろう。
出生前診断を受けたがために、夫の両親によって、胎児の命が危険に晒されたと言えなくもない。
だから出生前診断なんて不要だ、という意見も当然あろう。
しかし、不妊治療に代表される生殖医療は、ニーズに応じて進化する一方で、留めることは無理である。
となれば、出生前診断の「その後のサポート」を行う施設の充実を図るしかない。
ところで、今回のNスペで最も印象に残ったのは、二分脊椎症の妻が、自分に障害があることを負い目に感じ、自分の親、夫の親、自分に宿った命にまで「申し訳ない」と繰り返す姿だった。
彼女に負い目を感じさせてしまう側(社会)こそ、負い目を感じなければならない。